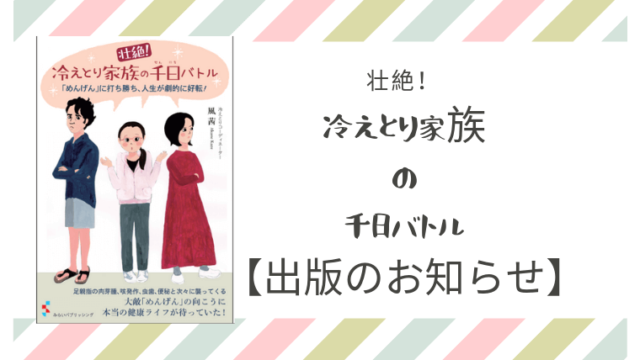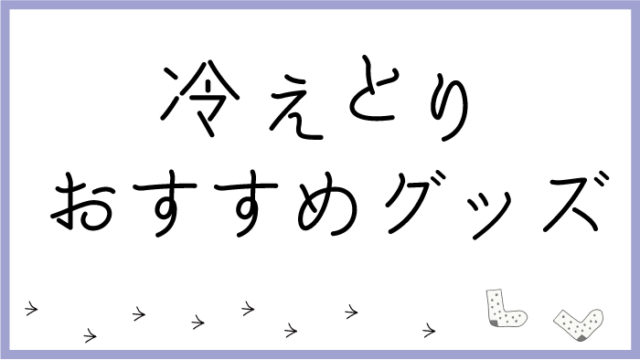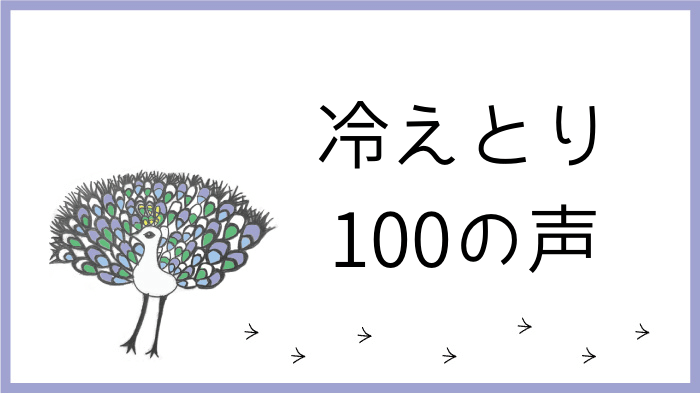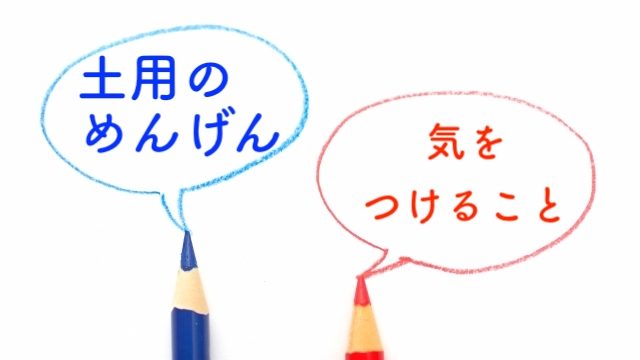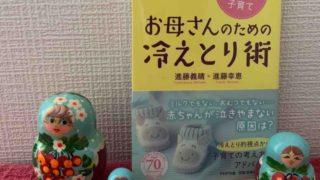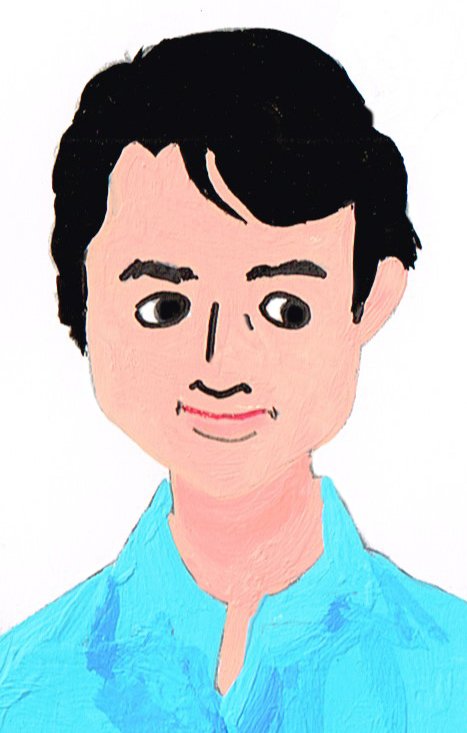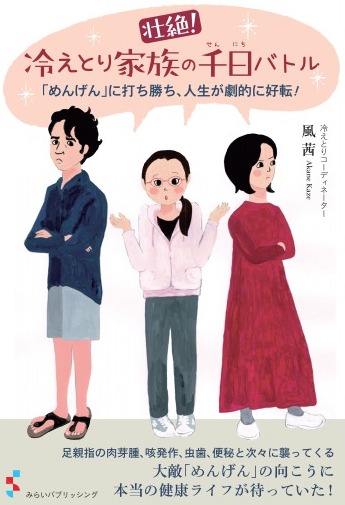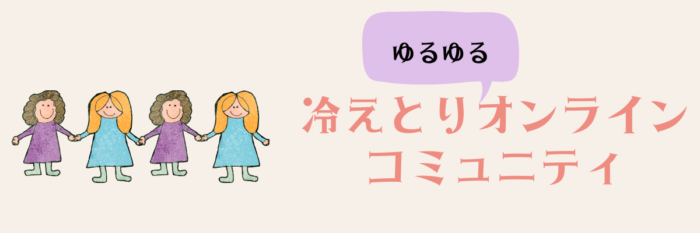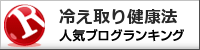【冷えとりと食】土用の丑の日にはうなぎを食べなくても良い理由

こんにちは。
冷えとりコーディネーターの風茜( @kazeakane1)です!
7月20日から土用に入りました。8月7日の立秋前の18日間を土用といいますが、冷えとりではこの土用には消化器の毒出しがあります。
この土用の毒出しは何かしら食べる機会が多くなったり、知らず知らずのうちに食べすぎになることもあります。
また夏の土用といえば、土用の丑の日がありますが、実は食べ過ぎの現代では、あえてうなぎを食べなくてもいいのです。
今日の記事は、冷えとりから考える土用の丑の日にうなぎを食べなくてもいい理由について考えてみたいと思います。
冷えとりでは土用は消化器の毒出し
土用は季節の変わり目の前の18日間あります。春夏秋冬4回の土用があります。
春は肝臓、夏は心臓、秋は肺、冬は腎臓
という臓器の毒出しがありますが、臓器の毒出しは年に1回だけです。
ところが、土用は年に4回もあります。
消化器をいかに酷使しているかわかりますね…
841さんのめんげん辞典では、土用の毒出しに起こる消化器の毒出しをこのように教えてくれています。
【消化器の毒出しでおこること】
吐き気、下痢、
便秘、耳鼻科関係の不調(鼻水、外耳炎、内耳炎、耳垢、めまいなど)、
目(かゆみ、痛み)、虫歯、歯茎の腫れ、口内炎、右の肩の痛み、
膝の痛み、怪我や事故
【消化器の毒出し中の心の状態でおこること】
くよくよ、安心安全を求める,利己、わがまま、優柔不断
どうして土用の丑の日にうなぎを食べるのか
土用には消化器の毒出しがあり、体調を崩しやすくなります。
次の季節に移る前に体調が整えられなくなるのです。
新しい環境にうつると、慣れるまで時間がかかるように新しい季節にうつる前の土用の期間に変化があるのです。
暑さから涼しさ、寒さから温かさに急に気温が変わると人は体調を崩しがちです。
昔から、土用の丑の日には「う」がつくものを食べて元気を出そうという習慣がありました。
この日にうなぎを食べるということを広めたのは、江戸のCM戦略からだったということをご存知ですか?
江戸時代に、夏は暑くて食欲が落ちてしまって、鰻屋が儲からなくて困っていたところ、平賀源内が丑の日にうなぎを食べるといいという戦略をたててくれ、爆発的に丑の日にうなぎを食べるようになったのですが、食欲が落ちているのは当たり前なんです。
夏には心臓の毒出しがあり、心臓からの毒を出しやすくするために、食欲がなくなっているのです。
食べないと免疫力が高まり、毒が出しやすくなります。夏の食欲がなくなったところに、あえて胃腸に負担をかけるものを食べる必要はないのです。
秋前の土用
7月20日から始まった今年の土用ですが、2022年の夏は雨の日が多くて涼しく、食欲もいつもの夏よりもあったと思います。
暑くもないのであまり汗もかいていません。
汗をかくことで毒出しは表面からでていくのに、今年はそれもできていないので、ぜひ食べ過ぎには気をつけたいところです。
土用の丑の日には、「う」のつくもので体によさそうなものは、
梅干し、うり、卯の花、
うどん(小麦アレルギーの人は気をつけて)、
烏龍茶、宇治茶
などです。
特に梅雨が明けて暑くなってきた土用の丑の日にはぜひ、塩分補給をかねて梅干しをうまく利用した食べ物がベストです。
食べ過ぎに注意して土用を過ごすと、次の秋の肺の毒出しが楽になりますよ!
(執筆者:冷えとりコーディネーター 風茜)
他にも土用のことはこちらもどうぞ!
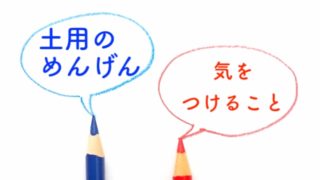
もしも土用に食べ過ぎてしまったときはこちらの記事をご覧くださいませ。