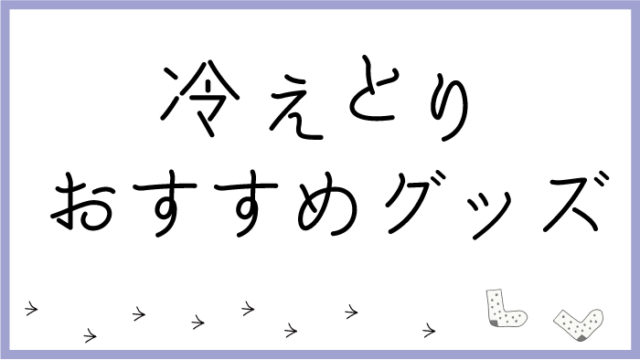長い間私は周りからいくら褒められても自分を認めることができませんでした。
それは、人の役に立ちたいと思いながらも、こんな自分が役に立つはずがないという自己評価がとても低かったせいです。
そんな私がコーチングと出会い、学んでいき、少しずつ自分を認められるようになっていくと、どんどんいいことが起こるようになってきました。
自分を認めることでそんなに簡単に運気が上がるはずがないと思う方もいるでしょう。今日の記事は、実際にコーチングで私が変化したことをお伝えします。
あなたも必ずいい方向に向かうはずです。
自分を認められない
子供の頃のわたしは、人前に出て話をするということが楽しくて楽しくて仕方がありませんでした。
小学3年生の時には、担任の先生から1学期終わりの通知表に、
「宏くんには、カラス5羽分の口が付いているようです。カアカアうるさいので、少しカラスを減らしてください」
と、書かれてしまうほどでした。もちろん書かれるだけじゃなくて、叱られるたびに強烈なビンタをくらってましたけど、(うちの両親はこの言葉にバカうけしてましたけど、今考えるとすごい表現だな〜。今の時代こんなこと教師が書いたら抗議殺到だろうな〜)
「いっそのこと10羽目指したら?あんたどうせ黙っとることなんかできんのやし」
「そうやね〜。宏くん、そうし〜。10羽目指しぃ」
「そうやそうや」
母の姉妹たちに囃されて、”しゃべり”に磨きをかけたわたしは、ビンタと拳骨の攻撃にも負けず、2学期の通利表には見事、
「減るどころか、10羽に増えてしまいました」
と、書かれる始末。それを見た親戚一同は大喜び。みたいな。その横で、高校教師の父親だけは複雑な表情を浮かべているみたいな。それでも父から、
「少しは、静かにせんか!」
みたいなことで叱られたことは一度もありませんでした。
両親も親戚のおばちゃんたちも、わたしの”しゃべり”には、一目置いているというのが、子供心にもわかっていたのだと思います。
だから、その当時のわたしの夢は、役者か海外特派員か、アナウンサーになることでした。どれもテレビカメラに向かって話をする仕事です。
「俺はしゃべりで有名になる!」
なんて、本気も本気。
でも、そんなわたしの夢を変える出来事が起きたのは、中学3年生の時でした。
中学校の学園祭で、わたしが脚本を書いて、演出をした舞台がウケにウケたのです。
昔話の山姥を題材にしたお芝居で、山姥役には学校の暴れん坊(ヤンキー的な人のこと)でガタイの大きかった男の子を起用しました。ボサボサ髪のカツラをかぶって、白い布に綿を詰めて作った巨大なオッパイを胸につけて、そのオッパイを振り回しながら村を襲って、赤ん坊にオッパイを食いつかせてそのまま奪っていく。その山姥退治を買って出る、村では誰からも相手にされなかったおばあさん役には、転校してきたばかりの目立たない女の子を説得して起用しました。
わたしは、最初に山姥に襲われてお尻丸出しのふんどし一丁で逃げ回るお調子者の農民役という一番恥ずかしい役を演じたのです。
山姥が村を襲うときには、当時、アイドルとして人気絶頂だった河合奈保子の歌をバックミュージックに流しながら、山姥がオッパイを振り回しながら河合奈保子と同じ振付をするという、公立の中学校の学園祭でやるにはギリギリの演出と、意表をついたキャスティングに、体育館となった会場が、先生までをも引き込んだ笑いの渦で埋め尽くされました。
この時の快感はわたしのそれまでの人生にとって最高のものでした。
自分の思い通りに人が笑ってくれる。身体中のアドレナリンが噴出した生まれて初めての経験だったかもしれません。
主役の彼女は、あまりのゲスな演出に最初は躊躇してましたが、終わった後には、
「私を選んでくれてありがとう。すごく楽しかった。自信もついたし」
そう言ってくれました。そして、
「なんで目立たない、ど近眼メガネをかけた私を選んでくれたの?」
そう聞かれたので、
「だって君は、すごい皮肉屋やろ。だから笑いのツボが分かる子やって思っとったもん」
「口も聞いたこともなかったのに、なんで分かるん?」
「分かるというか、なんとなくそう感じたから。絶対そうやと思って」
「風くんて、すごいね」
(そうか〜。俺はやっぱりすごいか〜)
ここでわたしは、自分が演じることよりも、本を書くこと、演出をすることに魅せられてしまったのです。
高校でも大学でも、演じることはあっても、熱は書くことと演出すること。
いつしか、表に出ることよりも、
「裏方に徹することの方が自分には向いている」
そう思うようになりました。
しかし、大学生の時に、舞台脚本家、舞台演出家としての自分の才能に限界を感じ、”しゃべる、書く”という夢を諦めました。
ただ結果的には、ライターという仕事につき、取材やインタビューでは”しゃべり”を生かし、原稿で”書く”を生かしながら”裏方に徹する仕事”についていたわけですから、人生は本当に不思議だと思います。
「宏のしゃべりは面白い」
「宏は人前でしゃべる仕事が向いているよ」
小さい頃からずっとそう言われ続けたことによって、根拠のない自信がずっと私の根底にあったのでしょう。
それが、ライターという仕事にも繋がったのだと思います。
とはいえ、ライターという仕事は、いくらインタビューが上手でも、文章で読者に感動を与えられなければ意味がありません。
”しゃべり”も”書く”も一流にならなければ、本当に良いものはできません。
10年書き続けても20年書き続けても、ちっとも上手に書けない。納得した文章が一度でも書けた試しがない。
結果、
この仕事に満足するという感覚がいつまでたっても得られませんでした。
要するに、
ライターとしての自分を認められない。
好きな仕事をずっとやってこれてるはずなのに、満足感が得られない。
どうして?どうして?どうして?……。
わたしは、この20年間、ずっとずっと、自分を認めてあげることができない状態が続いていました。

人は皆、誰かの役にたちたいもの
20数年間、この仕事で食べてこられたのだから、才能が全くなかったわけではないと思います。
「君は記者として優秀だよ」
「先日の記事はとても面白かった」
「あの野球選手からよく、あんなコメントを引き出せたね。さすが風だ」
そんな言葉をいただいたときは、本当にありがたく、その瞬間は嬉しいのですが、それでもわたしの気持ちは晴れません。
結局は、
自分で自分を認めてあげられないのだから同じなのです。
「この気持ち、頼むから誰かなんとかしれくれっ!」
ずっとずっと私があげていた心の悲鳴です。
それと同時に、歳を重ねるごとに強くなっていったもう一つの思いもありました。
「自分が社会に貢献しているという実感が欲しい」
「人の役に立っているという実感が欲しい」
何も私だけでなく、人間誰しもある程度の年齢を重ねると、「社会貢献」という思いが強くなるといいます。
私も全く同じでした。
取材をして文章を書いて、それが雑誌に掲載されても、正直、「社会貢献」という実感がない。結果、社会貢献になっているのかもしれないけれど、生の声をどうしても求める自分がいたのです。これはただのエゴかもしれません。エゴと知りつつも、求めないではいられない自分が確かにいる。
「人から感謝されたい」「風さんのおかげです」
と、言われたい。
その声に素直に従ったのが、このブログなのです。
間もなく1年半になりますが、多くの読者の方々の声を頂くことが、モチベーションとなり、ここまで続けてこられましたが、それでも、やはり納得できない。何かが、どうしても足りない。それは何か?
「もっともっと直接的に、困っている人や前に進めない人、もっともっと輝いて自分にはもっと何かができると思っている人のために何とかできる方法がないのか?」
そんな時に出会ったのが、コーチングだったのです。

自分を認めてあげるということ
コーチングには、「自己基盤」という言葉があります。
~コーチは、常にクライアントのロールモデル(模範)であることを目指しています。その前提として、自分自身をよく理解し、自分自身に対しての肯定的な思いを持ち、それを相手に開示できることが大切です。~(text by 銀座コーチングスクール)
コーチングと出会う前、わたしは自分自身をよく理解してはいましたが、そんな自分の全てに対して肯定的な思いを持つことはできないでいました。
コーチングと出会い、わたしを担当してくださるコーチと出会い、セッションを重ねるにつれて、わたしは気がつくと、自分の今ある姿、今ある状況をすべてそのまま認められるようになっていたのです。
これは、本当に驚くべき変化でした。
わたしは、コーチングの勉強を始める前まで、
「コーチとして人と接するということは、何か心理学的なテクニックを使ってカウンセリングのようなことをするのだろう。そのための技術さえ習得すればコーチになれる」
と、思っていました。
しかし、全く違っていました。確かに、コーチとして最低限の知識やスキルは必要になりますが、わたしがコーチと行っていることは、
コーチはわたしの話を聞き、わたしはコーチの話を聞く。
コーチは自分のことをわたしに話してくれて、わたしは自分のことをコーチに話します。
その中で、わたしは、
自分の大きな欠点だと思っていたことが、実は、自分が思っていたほど大きな欠点ではないことに気づかされ、
自分の長所が、自分にとって、ものすごく大きな武器になるということに気づかされたのです。
そして、「気づかされた」と書いてますが、コーチから、「あなたの欠点は大きくないんだよ」とか、「あなたの長所は武器になるんだよ」とか、指摘されて気づいたのではありません。
自分の内なる声に気づかされたのです。
「人間には必ず欠点がある。長所だけの人間なんて存在しない」
「逆に長所だけの人間も存在しない」
「そもそも”生”には、そういった大前提がいくつもあって、それは決して覆るものではないのに、それを否定することに意味がない」
「それら全てをひっくるめて、自分という人間が生かされているのだから、そこを認めることから始めよう!」
「欠点があるから長所があるのだし、長所があるから欠点が補える」
「そのどれもが一つでもかけてしまったら、それが仮に長年忌み嫌っていた欠点だとしても、果たして自分を認めることが本当にできるのだろうか?」
コーチとの会話が進むにしたがって、わたしは、今ままで考えもしなかったことを考えるようになりました。
今まで全く機能していなかった脳細胞がこの歳になって動き出したような感覚です。
1日に何万個も脳細胞は死滅しているということですが、反対に新しい脳細胞が生まれ、新しい毛細血管が脳の隅々にまで根を伸ばしていくような感覚が生まれたのです。

感じることが大切
そして、最近、感じることは…。
そう、考えているのではなく、
「感じている」
そういう感覚が芽生えてきたというのでしょうか。
この感覚は、コーチングを受けた人にしかわからないものなのかもしれませんね。
例えば、
こういうパターン、よくありませんか?ちょっと、思い出してみてください。
家から一歩出た瞬間に、
「あれ?今日、雨が降るのかな?」
そう感じます。でも、天気予報では今日は雨の確率はゼロパーセントだった。そこで、あなたは考えます。どうしようかな〜?
「いやいや、そんなことはない。天気予報では雨が降らないって言っていたのだから降るわけないか。勘違いか」
で、結局、帰宅時には土砂降りになってしまった。
「ああ〜、あの時、降るんじゃないかな〜って思ったのに〜!」
こういうパターンはどうです?
あなたは、ショップに服を買いに行きました。何を買うかだいたい決めていました。
ショップに入った途端、目に入ったパンツにすすす〜っと引き寄せられます。一目で気に入りますが、
「そういえば、パンツも新しいのが欲しいと思ってたな〜。いやいや、ブラウスを買いに来たのだから、ブラウスを買ってからにしよう」
そう考えてブラススを見に行きますが、欲しかったものが見当たらない。仕方なくパンツのところに行きますが、もうなくなっていた。
「ああ〜。あの時、手に持っていればよかった〜」
なんてことです。
あと、こういうこともありませんか?
わたしの娘の音は、電車が大嫌いです。すぐに気分が悪くなるのです。理由を聞くと、
「なんか、変な人が必ず隣に立っていたり、座ったりするんだよ。その人から変な匂いがしてくるというか…。なんか嫌だな〜って感じた人がいたら、必ず隣に来るの。だからいつも気持ち悪くなる」
コーチングと出会う前の私だったら、こう言っていたかもしれません。
「そんなこと言ってたらどこにも行けないよ。電車は常に満員なんだし、とにかく環境に慣れなくちゃ。ガマンガマン」
実際には、こう言ってあげました。
「その感覚は正しいんだよ。人間は、自分にとって危険なものを察知する能力がある。音はきちんと危険を察知できているから気持ちが悪くなるんだよ。ガマンする必要は全くないから、少しでも嫌だな〜とか、離れたいな〜っと感じたら車両を移ったり、降りても構わないんだよ。そういう時は遅刻しても構わない」
「ガマンしなくていいの?」
「いいよ。乗りたくなかったら乗らなくてもいい」
「自分が変なんだってずっと思ってたよ。だから、いつもガマンしてた」
「それと、もう一つ。電車に乗った瞬間とか、乗っている時にふと何かを感じて、パッてそっちの方を見ることがあるでしょう?」
「うん。あるある。そういう時って、おじさんと目と目があったりする」
「そういう時は、絶対にそっちにいかないこと。そっちを見ないこと。なんだったら離れること。自分の感覚を疑わないこと」
「うん。わかった。じゃあ、綺麗なお姉さんとか、親切そうな女の人のそばにいればいいのかな〜?」
「だったら安心?」
「うん。大抵、そういう人は親切だから」
「だったらそうしてみれば?」
「うん。そうする」
以来、音が電車に乗って「気持ちが悪い」ということは無くなりました。遅刻したことも一度ありません。先日は雨でびしょ濡れで電車に乗ってきた音に、女子大生風の女の子が自分の持っている傘をくれたそうです。
「この傘、安いからあげるね」
そう言って頭も持っていたハンカチで拭いてくれたそうです。

思い出してください。
わたしたちは、子供の頃、考えて生きてはいませんでした。
感覚で感じて、感じたことに素直に従って生きていました。
つまり、無意識のうちに、自分を認めてあげていたのです。
でも、それだけでは社会生活を渡ってはいけません。「考えて生きろ!」そう言われて、思考ばかりに頼るようになっていきます。そして、いつしか、自分の感覚を疑うようになってしまったのです。
「感じろ!そして、考えろ!」
せめて、そう教えてくれていたら、もっと人は「感覚」を大切にしていたかもしれませんね。
自分の感覚を疑う = 自分を認めない
「ママ友と仲良くできない。でも、子供のために仲良くしなければいけないのだよね。ガマンガマン」
そうではなくて、
気の合う人と仲良くすればいい。仲良くしたい人と仲良くすればいい。気の合わない人には自分からは近づかない。
自分を認めてあげる第一歩は、
自分の感覚を認めることから始まるのです。
(執筆者:心の冷えとりコーチ 風宏)

風 宏(Kaze Hiroshi)
心の冷えとりコーチ
冷えとり歴13年目。靴下6枚ばき、半身浴20分。最近お酒がやめられるように変化した2015年2月4日より、女性のための問題を解決するブログを開始。2016年9月GCS認定プロフェショナルコーチ資格取得。女性のための心の冷えとりコーチング講座も開催。